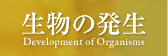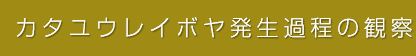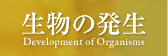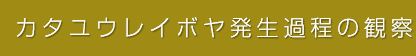| [03] 1細胞期における卵内の細胞質の動きは大きく2つの段階に分けられる。未受精卵ではマイオプラズムは動物極以外の表層に局在している。受精直後,表層のアクチンネットワークが収縮し,表層のマイオプラズムを植物極に局在させる。この過程は,第一細胞質再配置と呼び,約5分で終了する。この過程は,アクチン繊維が移動の原動力として働いている。
その後,表層のアクチンネットワークの収縮に伴い植物極付近に移動した精子核から精子星状体が発達し,後方赤道部へと移動を開始する。この精子星状体の動きに伴って,植物極のマイオプラズムは後方赤道部へと引きずられ,新月環を形成する。この過程は,第二細胞質再配置と呼び,精子星状体の移動の続く第一卵割まで続く。この過程では,微小管が移動の原動力として働いている。この新月環を正中面で二分するように卵割面が入り,2細胞期となる。その後,植物極後方の予定筋肉割球がマイオプラズムを受け継いでいく。 |
|