| 10-3 |
| 原価計算 | 諸藤裕美 |
|
第10章 標準原価計算
10-2 標準原価計算のプロセス |
|
標準原価計算は、原価差異の把握・計算を行うタイミングの違いにより、期末に原価差異を把握・計算する「アウトプット法(output method)」と、原価財のインプットが行われるつど、原価差異の把握・計算を行う「インプット法(input method)」とが存在する。ここでは、「アウトプット法」に関して説明を行う。
原価標準(cost standard)とは、製品機的に結びついて常時継続的に行われる場合には、標準原価計算制度とよばれる。
標準原価計算の主な目的としては、(1)原価管理目的、(2)公表財務諸表作成目的、(3)予算編成目的、(4)記帳の簡略化・迅速化、の4つがあげられる(原価計算基準40)。1単位あたりに標準的にかかる原価をいう。まず、各原価要素ごと(直接材料費、直接労務費、製造間接費)に製品1単位あたりの標準原価を算出し、それらを合計することにより設定される。
原価標準は、会計年度開始前に設定され、下図のような標準原価カードに記載し、事前に関係部署に指示することにより、現場の人々の原価目標達成を動機づけることを可能とする。
図表8-1 標準原価カード
| 標準原価カード | |||
| 直接材料費 | (標準単価)500円/kg | (標準消費量)3kg | (金額)1,500円 |
| 直接労務費 | (標準賃率)700円/時間 | (標準作業時間)2時間 | 1,400円 |
| 製造間接費 | (標準配賦率)500円/時間 | (標準配賦基準)2時間 | 1,000円 |
| 原価標準 | 3,900円 | ||
各原価要素ごとの標準は以下のように設定する。
原価標準は、タイトネス(tightness)の違いによって主として以下の3種類に分類される。「原価計算基準」で認められているのは、(2)と(3)である(原価計算基準4(一)2)。
なお、原価標準はさまざまな目的(8-1参照)に使用されるので、実態に即した標準となるよう適宜改訂する必要がある(原価計算基準42)。
標準原価 = (上記(1)で算出した)原価標準×当期の生産実績
標準原価は、上記(1)で各原価要素ごとに算出した原価標準に当期の生産実績をかけて計算する。なお、原価標準は完成品1単位あたりにたいして算定しているため、生産実績は当月投入完成品換算量を用いる必要がある。当月投入完成品換算量は、「完成品数量−月初仕掛品完成品換算量+月末仕掛品完成品換算量」によりもとめる。
上記(2)で計算した標準原価と比較するため、当期の実際原価を各原価要素ごとに計算する。
標準原価差異(standard cost variance、原価差異ともいう)とは、上記(2)で計算した当期の生産実績にたいする標準原価と、上記(3)で計算した当期の実際原価との間に生じた差額をいう。つまり以下の式から、各原価要素ごとに標準原価差異が計算される。
直接材料費差異(direct material cost variance) = 標準直接材料費−実際直接材料費
直接労務費差異(direct labor cost variance) = 標準直接労務費−実際直接労務費
製造間接費差異(overhead cost variance) = 製造間接費標準配賦額−製造間接費実際発生額
計算された差異額がマイナスの場合は、実際原価があらかじめ定めた標準原価よりも多くかかってしまったことを意味するので、「不利差異(unfavorable variance)」あるいは「借方差異(debit variance)」という。差異額がプラスの場合は、標準原価よりも少ない原価ですんでいるので、「有利差異(favorable variance)」あるいは「貸方差異(credit variance)」という。
上記(4)で各原価要素ごとに算出された標準原価差異について、その原因の分析を行う。
直接材料費差異は、価格差異(material price variance)と数量差異(material quantity variance)に細分される。数量差異は消費量差異(material usage variance)ともいう。
図表8-2 直接材料費差異の分析
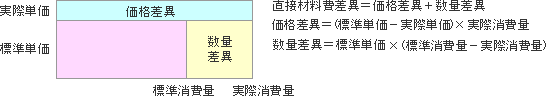
価格差異は、標準単価と実際単価の差により生じた差異であり、市場価格の変動・購買部門の不適切な材料仕入方法などにより生じる。それゆえ、生産現場にとって管理不能な部分である。一方、数量差異は、効率的に生産を行った場合の消費量と実際の消費量との差により生じる差異であり、生産能率の良し悪しによって生じる。それゆえ、生産現場にとって管理可能な部分である。
直接労務費差異は、賃率差異(labor rate variance)と作業時間差異(labor hour variance)に細分される。
図表8-3 直接労務費差異の分析
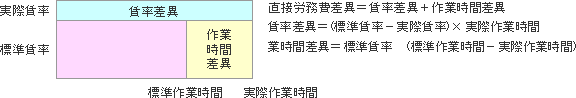
賃率差異は、標準賃率と実際賃率の差により生じた差異であり、作業員のシフトの変更などによって生じる。それゆえ、生産現場にとって管理不能な部分である。作業時間差異は、能率的に生産を行った場合の作業時間と実際作業時間の差により生じる差異で、生産能率の良否をしめす。それゆえ、生産現場にとって管理可能な部分である。
第3章で説明したように、製造間接費予算の設定方法には固定予算と変動予算がある。それぞれの場合の差異分析についてみていく。
差異分析は、差異をいくつの要因に細分するかにより、2分法、3分法、4分法などが存在する。
3分法は、製造間接費配賦差異を「予算差異(budget variance)」、「能率差異(overhead efficiency variance)」、「操業度差異(volume variance)」に細分する。「予算差異」は、実際操業度のもとでの製造間接費予算額と実際発生額との差額である。「能率差異」は、標準操業度と実際操業度が異なるために生じた配賦差額で、作業能率の良否をしめす。能率差異に固定費部分を含めない方法(第1法)と含める方法(第2法)とが存在する。「操業度差異」は、基準操業度と標準操業度(第1法)あるいは基準操業度と実際操業度(第2法)とが異なるために生じた配賦差額で、生産設備の利用状況の良否をしめす。図示すれば以下のようになる。
図表8−4 製造間接費差異の分析(変動予算)
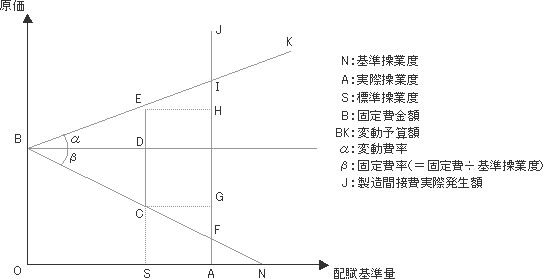
製造間接費差異 = 予算差異 + 能率差異 + 操業度差異
予算差異 = 製造間接費予算額(変動予算額) - 製造間接費実際発生額(= IJ)
能率差異 = (第1法)変動費率 x (標準操業度 - 実際操業度)(= HI)
または、(第2法) 標準配賦率 x (標準操業度 - 実際操業度)(= FG+HI)
操業度差異 = (第1法)固定費率 x (標準操業度 - 基準操業度)(= SC)
または、(第2法)固定費率 x (実際操業度 - 基準操業度)(= AF)
第1法には、固定費の能率差異という管理不能な部分を能率差異から除くことができるという利点が、第2法には、もし基準操業度として実際的生産能力を用いる場合には、操業度差異が不働費 (idle costs)をより純粋にしめすことができるという利点が存在する。不働費とは、生産能力を遊休にしたためにこうむる製造間接費の損失をいう。このことから、原価管理目的を重視するならば、(第1法)のほうが適している。
4分法は、上記第2法の能率差異を変動費部分と固定費部分に2分する方法である。つまり、以下のように差異分析される。
予算差異(消費量差異(spending variance)ともいう)
=製造間接費予算額(変動予算額)−製造間接費実際発生額(=IJ)
変動費能率差異(variable efficiency variance)=変動費率×(標準操業度−実際操業度)(=HI)
固定費能率差異(fixed efficiency variance)=固定費率×(標準操業度−実際操業度)(=FG)
操業度差異(不働能力差異(idle capacity variance)ともいう)
=固定費率×(実際操業度−基準操業度)(=AF)
2分法は、4分法における予算差異・変動費能率差異部分を管理可能な部分として、固定費能率差異・不働能力差異部分を管理不能な部分としてとらえる方法である。
管理可能差異(controllable variance) = HJ
管理不能差異(uncontrollable variance)(操業度差異ともいう) = AG
但し厳密には、管理可能差異のなかにも管理不能な原因による部分が、管理不能差異のなかにも管理可能な原因による部分が存在する。
ここでは3分法についてのみ触れる。固定予算のもとでは操業度に関わらず予算が一定額なので、予算差異は固定予算額と実際発生額の差の部分になり、操業度差異は実際操業度と基準操業度の差に標準配賦率をかけて算出される。
図表8-5 製造間接費差異の分析(固定予算)
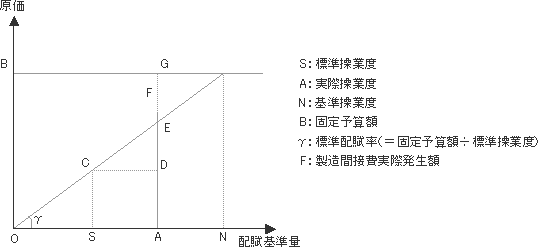
予算差異 = 製造間接費予算額(固定予算額) - 製造間接費実際発生額(= FG)
操業度差異 = 標準配賦率 x(実際操業度−基準操業度)(= EG)
能率差異 = 標準配賦率 x(標準操業度 -実際操業度)(= DE)
しかし、製造間接費のなかには、操業度の変化に伴い発生額が変化する変動費も存在する。それゆえ、実際操業度と基準操業度が乖離している場合、固定予算額と実際発生額を比較しても、原価管理目的上はあまり意味がない。
上記(5)で明らかにされた差異の原因究明が行われ、その結果が経営管理者に報告される。また、必要に応じて改善策を検討する。
| 10-3 |