human and environment
3-2. 母乳に含まれる
生命維持必須な無機ミネラル
生命維持必須な無機ミネラル
- ヒトからみた環境 - 玉利 祐三
生命維持に欠くことのできないミネラル、換言すれば生体にとって欠くことのできない必須元素、その量が非常に低濃度でも正常な代謝を行ううえで必要なのが必須微量元素である。栄養として吸収される場合、ミネラル(必須元素、必須微量元素)の量ではなく、質(元素の化学形)が重要である。また、食事から摂取するときの「食べ合わせ」も重要である。
必須元素・必須微量元素の濃度と生存率
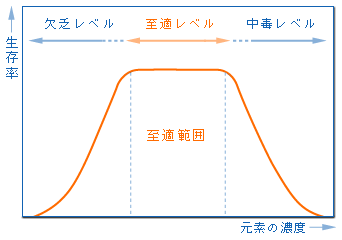
- 必須元素・必須微量元素の必要所要量
- 必須元素あるいは必須微量元素は、生体にとって摂取量が多すぎ過剰になれば、その元素の毒性すなわち機能的障害が現れ、毒性が強い場合には死に至ることもある。
逆に、摂取量が不足すれば正常な代謝機能を果たすことが困難となり、病的疾患いわゆる欠乏症が現れ、極端な場合には死に至ることもある。
どちらにしても正常な代謝を行うべく体内で正常な濃度レベルを保持しようとする、すなわち内部環境を一定に保持しようとするホメオスタシス(homeostasis:恒常性)現象が認められる。従って、生物は、微量元素の必要量の範囲をうまく保って、生命を維持させている。
- 必須元素・必須微量元素の種類と作用
- 生物体は、ほとんどが水と有機化合物で構成されているので、その構成元素として、水素(H )、酸素(O)、炭素(C)、窒素(N)、リン(P)、イオウ(S)の6元素は言うに及ばず、体液や骨格中に含まれるナトリウム(Na)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、塩素(Cl)の5元素も古くから知られていた(原子番号でいえば20番までの元素)。これらの元素は、生物体の99%を構成するので、必須常量元素と呼ばれている。その残りの1%が必須微量元素と呼ばれるものである。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 必須微量元素の化学形態と摂取率
- 量のみならず化学形態で決まる毒性
微量元素の必須性と毒性の両方を考えるとき、その摂取量はもとより摂取される元素の化学形態が重要となる。たとえば、水銀といっても無機水銀とメチル水銀(有機水銀)では、生体内での作用は全く異なる。
無機水銀を摂取すると、その吸収率は低く、吸収されても主として肝臓に蓄積される。一方、メチル水銀は効率よく吸収され、体内では脳に集まり、特有の神経症状を示す(水俣病)。他の元素としてヒ素の例をあげる。
森永ヒ素ミルク中毒事件は、無機ヒ素化合物がミルク中にあやまって混入(不純物であるヒ素を多く含むリン酸ナトリウムを粉乳に添加したため:ヒ素として10 ppm 混入)され、多数の乳児の死と中毒症状(色素沈着、筋萎縮、骨髄障害)をまねいた。
しかし、海草のヒジキやウニには多量のヒ素(時には 100 ppm)が含まれており、これを食して中毒したという報告はない。従って、これらの海産物中のヒ素は有機ヒ素として存在し、無毒化されているものと考えられている。
このように同じ元素であっても、同じ濃度であってもその元素の化学形態が異なれば、生体に対する作用は大きく異なるので、元素の毒性と元素濃度を考える場合には注意が必要である。
- 食べあわせとミネラル摂取率
食事から摂取される微量ミネラル、すなわち元素の吸収率を考える場合、それと共存する成分が重要である。例えば、カルシウムはビタミンDあるいはビタミンCを同時に摂れば、腸からの吸収率が高くなる。それは、食事により摂取したカルシウムは、胃(胃酸)で溶解され、ついで小腸に移される。
しかし、摂取時にカルシウムとビタミンDあるいはビタミンCがあれば、小腸では水に可溶性の化合物(カルシウムの水溶性キレート)が生成して、カルシウムは沈殿しにくくなり、カルシウムの吸収率が高まるといわれている。
逆に、シュウ酸、フィチン酸が共存すれば、カルシウムは水に不溶性のカルシウム塩となり、腸からは吸収されない。また、脂肪(リン脂質)を同時に摂れば、カルシウム石鹸(脂肪酸のカルシウム塩)が生成して沈殿物となり、カルシウムは小腸から吸収され難くなる(京都大学食糧科学研究所、安本教傳による)。 微量の必須ミネラルとして重要な鉄、亜鉛、銅等の吸収についても上記と同様の考え方が成立する。 鉄は胃中では、胃酸という酸性(低pH)で溶解しているが、中性である小腸に達すると鉄の水和酸化物となって沈殿し、この沈殿に亜鉛、銅、セレン等のさらに微量の必須ミネラルがくっついて沈殿(共同沈殿)し、腸からの吸収は困難となる。
しかし、ビタミンC(L−アスコルビン酸)、クエン酸、シュウ酸、食酢(酢酸)等の有機酸が共存、すなわち一緒に食すると、鉄は水溶性キレートである有機酸鉄となり、腸では沈殿しないため、逆に腸からの吸収効率は増加する。
食事中に野菜を十分にとること、酢のものをとること、食後に果実をとること、そして日本茶を飲むことは、これらに含まれるビタミンC等の各種有機酸を摂取することになり、この結果必須ミネラルの吸収率が高まる。
このように伝統的な日本の食事スタイルは、微量の必須ミネラルを摂取するうえで、極めて効果的であり、また必須微量ミネラルをとることによる病気予防の効果を合わせて考えると、非常に興味深い。
その一方で、微量ミネラル(微量元素)の摂取量、適正量を問題にするとき、その微量元素の化学形および共存する成分を考慮しなければ正確な栄養摂取の評価はかなり難しくなる。 以上のように、健康な身体を維持するには、日々、一定必要量の必須元素および必須微量元素を摂取すること、換言すれば栄養ミネラルを摂取することが必要である。 しかし、今日のように多種類の食品を「いつでも、どこでも買える」飽食の時代、食品に恵まれた社会では、食品の選択が重要となる。電子レンジの普及により冷凍食品の種類が豊富になってきたこと、それに伴って防腐剤の添加、さらに様々な色素が添加された色鮮やかな菓子・食品類などが反乱している社会でもある。
食品の加工工程が多くなればなるほど、オリジナルの栄養ミネラル成分が除かれいくことになる。タンパク質、脂質、糖質については、おそらく十分すぎるぐらい摂取している、あるいは摂取することは簡単であろうが、適切な必須微量元素の摂取については、加工食品が氾濫している現在社会において特に注意する必要がある。
以上のように、健康な身体を維持するには、日々、一定必要量の必須元素および必須微量元素を摂取すること、換言すれば栄養ミネラルを摂取することが必要である。 しかし、今日のように多種類の食品を「いつでも、どこでも買える」飽食の時代、食品に恵まれた社会では、食品の選択が重要となる。電子レンジの普及により冷凍食品の種類が豊富になってきたこと、それに伴って防腐剤の添加、さらに様々な色素が添加された色鮮やかな菓子・食品類などが反乱している社会でもある。
食品の加工工程が多くなればなるほど、オリジナルの栄養ミネラル成分が除かれいくことになる。タンパク質、脂質、糖質については、おそらく十分すぎるぐらい摂取している、あるいは摂取することは簡単であろうが、適切な必須微量元素の摂取については、加工食品が氾濫している現在社会において特に注意する必要がある。
- 食べあわせとミネラル摂取率