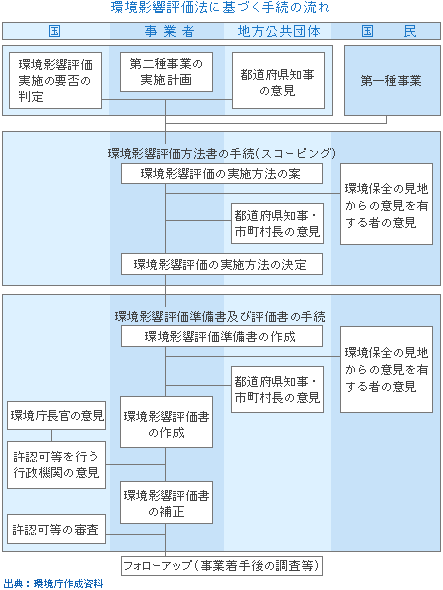|
human and environment
1-4-2. 環境アセスメントの概要
- 環境法・環境政策 - 大久保 規子
- ステップ1
下の図を見て,次の点を考えてみましょう。
-
A. 誰が環境アセスメントを行うのか。 解答
↓
事業者。
B. スクリーニング(screening)とは何か。 解答
↓
事業の内容,規模,地域の環境特性等を踏まえ,環境アセスメントを実施するか否かを個別に判断する手続。
C. スコーピング(scoping)とは何か。 解答
↓
環境影響に係る調査を開始する際,地方公共団体,住民,専門家等の意見を幅広く聴いて,具体的な評価範囲を個別に絞り込んでいく手続。
D. 環境破壊を心配する人はいつ意見が言えるのか。 解答
↓
- (1) スコーピング段階と準備書段階では,だれでもが意見を言える。
- (2) 環境庁長官は,評価書段階で,必要に応じて意見を言える。
- (3) 都道府県知事は、スクリーニング段階、スコーピング段階及び準備書段階で言える。また、市町村長は、スコーピング段階と準備書段階で言える。
E. 誰が審査するのか。 解答
↓
事業免許等を行う者(許認可庁)。
- ステップ2
なぜ,事業者がアセスを行うべきなのでしょうか。また,この仕組みには,どのような問題が考えられますか。
環境汚染の対策費用は汚染者自らが負担すべきであるという「汚染者負担(PPP)の原則」に基づいて,事業者がアセスの実施者とされた。だが,事業者自らが行うと,客観的,公正な審査ができないとの批判がある。そこで,例えば,ドイツでは,第三者がアセスを行い,事業者はコストだけを負担するという仕組みが採られている。
- ステップ3
なぜ,スクリーニングが必要なのでしょうか。
環境への影響は地域によって差があり,あらゆる場合を想定した基準を作るのは困難である。また,あらかじめ対象事業を限定列記すると,事業を規模要件ぎりぎりに縮小・分割するなどして,環境アセスメントを回避するおそれがあるため。
- ステップ4
なぜ,スコーピングが導入されたのでしょうか。
従来の閣議アセスでは,技術指針の中に調査項目等が列挙されていたが,論点を明確にした重点的な評価ができず非効率であるとの批判が強かったため。
|