前章で述べたが、正常なホルモン作用はレセプタ−を介して重要な臓器に働きかけ、生体機能をコントロ−ルすると共にホメオスタシスを保ち、健康な生命活動を維持するのである。例えば、体内の内分秘腺で合成されたステロイド・ホルモンは血流に乗って標的臓器に到達すると、レセプタ−に結合し、DNA(遺伝子)に情報伝達することにより機能性蛋白の合成が始める。
諸種のホルモンは、それぞれ結合するレセプタ−が厳密に決まっている。つまり、ホルモンとレセプタ−の関係が鍵と鍵穴に例えられる所以である。ところが、女性ホルモン(エストロジェン)を例にとると、これに対応する鍵穴はそう厳密でなく、他の鍵(化学物質など)でも開いてしまうと言われている。すなわち、環境中から体内にとりこまれた外因性の化学物質がニセの女性ホルモンになりすまし、ホンモノの内因性女性ホルモンをおしのけ、レセプタ−と結合して細胞核内に入り、DNAにニセの指令(情報伝達)を出すことにより、内分泌系を攪乱し、結果として生殖器の形成やその役割を阻害するとされている。また、本来の内因性ホルモンは必要以上に分泌されたり、役割を終えると分解、消滅する。つまり、フィ−ドバック機能を持ちホメオスタシスを保つのであるが、ニセのホルモン(化学物質)では、いつまでも分解せず標的器官に存在しニセの指令を出し続けるため、生殖異常、乳癌や子宮内膜症などを引き起こすと考えられている。
ちなみに、ほ乳類では胎生期(ヒトでは妊娠6週目にあたるり、ちょうど性の分化の時期)が非常に性ホルモンに敏感な時期であり、この頃に大量の女性ホルモンに曝露され続けると、不可逆的な反応(もう元に戻らない)を引き起こすことが知られている。そして、出生後の子供に内分泌系、生殖系、免疫系、及び神経系にまでも深刻な影響が出るのではないかと言われている。
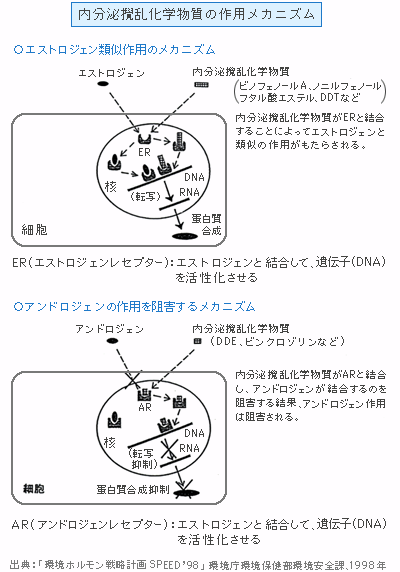
内分泌攪乱化学物質がレセプタ−に結合して生じる反応には二通りの作用が考えられる。
(1)PCBやDDT等の有機塩素系化学物質、ノニルフェノ−ルやビスフェノ−
ルA等のプラスッチク系可塑剤として使われる化学物質が、エストロジェ
ン・レセプタ−に結合することによって、内因性のエストロジェン(女性ホ
ルモン)と類似の作用を及ぼす。
(2)DDTの代謝産物であるDDEやビンクロゾリンなどの一部の農薬類はアン
ドロジェン・レセプタ−に結合し、内因性のアンドロジェン(男性ホルモ
ン)の正常な作用を阻害する。
一方で、ある化学物質ではホルモン・レセプタ−に直接結合するのではなく、細胞内のシグナル伝達経路に働きかけることにより、遺伝子を活性化させて機能性蛋白を産生することが明らかにされている。例えば、ダイオキシンはエストロジェン・レセプタ−やアンドロジェン・レセプタ−に直接結合せず、ある種の細胞内蛋白質に結合することにより、遺伝子を活性化し間接的に正常なエストロジェンの作用に悪影響を与え続けるといわれている。
ところで、内分泌系の医薬品、つまり合成ホルモンは通常レセプタ−に影響を及ぼすことによって作用を発揮するが、その中には本来のホルモンの作用を増強する物質も存在する。例えば、DES(ジエチルスチルベストロ−ル)はエストロジェン・レセプタ−に結合し、エストロジェンのシグナルを遺伝子に与え続ける。その結果、ガン化、あるいは妊娠中であれば胎児の奇形などが発現するといわれている。
内分泌攪乱物質は、ホルモンの作用を模倣、増強または阻害する 天然生成物または合成化学物質である。以上に化学物質の生体への作用メカニズムについて述べてきたが、厚生省「内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会・中間報告」では、ホルモン・レセプタ−への作用機序について次のようにまとめている。
|