human and environment
1-2. 世代間倫理
- 地球環境問題の解決に向けて - 谷口 文章
- A. 通常の時間軸における世代間論理(環境論理の基本問題)とは?
- 環境倫理学の重要なテーマの一つである世代間倫理とは、現在まだ存在していない人格、すなわち未来世代の人格に関しての「権利と義務」についての新しい解釈を要請する。それは、未来世代の権利や人類の生存の権利をめぐる問題をテーマとする。従来、人格同士の権利と義務の関係が扱われてきたが、それを動植物や自然物にまで拡大したり、存在しない未来の人格にまで拡張する考え方を通じて、地球環境を回復し保全するために、現代人の権利と義務は何なのかを追求するものである。
たとえば、現代と未来の世代間における資源や環境保全の公平な配分の問題だけでなく、男性の精子数の減少や子宮内膜症の増加などは、環境ホルモン(外因性内分泌攪乱化学物質)の有害化学物質による汚染と考えられ、世代間倫理の新しい型として、深刻に考えられなければならない問題である。
- B. 圧縮された時間軸における世代間倫理(環境倫理から生命倫理へ)とは?
- ところでヘッケルは、「個体発生は系統発生を繰り返す」と述べている。人間の生誕や個体の発生過程においては、内に圧縮された40億年の生命の歴史的な時間を繰り返す。個体発生の経過において人間は、卵子と精子の受精を経たのち、胎児としての形が出来上がるまでに、魚類、両生類、爬虫類、哺乳動物などの形態をとることによって、圧縮された40億年の生命の歴史を繰り返している。こうして、人間が生まれたり個体が発生するメカニズムは、自己創出的に生じるのである。
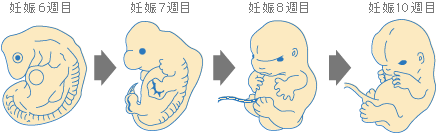
魚類−両生類−爬虫類−哺乳動物 進化の過程
- このことから、生命は圧縮された時間軸において「入れ子状」にすべての生命と連なっていることがわかる。この現象は、エコシステムをベースとする自然環境が空間的に「入れ子状」になっているのと対応している。
このことを考慮するなら、親が妊娠中にスクリーニングなどの結果から人工中絶することは、一方的な離別行使としての世代間倫理の問題と根を同じにしていることがわかる。つまり「環境倫理」と「生命倫理」は根底で共通しているのである。
- C. 生命倫理( bioethics )と環境倫理の共通の問題 −世代間を通じて−
- 生命体の生長・維持・老化・死というのは、個々の生命現象の瞬間が連続して連なっていく過程である。そのため、胎児と新生児との世代間の分かれ目や生と死の区分などは非常にあいまいである。さらに、確立されているように思える法律でもあいまいである。民法においては身体全体が外に出た時点において人格を認めるのに対して、刑法は産道から頭が出た時点を人格として認めるようにである。
こうして、胎児がどこで人間として認められるのか、人間がどこで人格として認められるのかという「区切り」の問題は、DNAによる生命現象の生が死を内包している構造(アポトーシス apotosis )や文化や慣習の相対的な相異によって可変的であり一律に確定していないのである。
さらに、既述の人工中絶や胎児のスクリーニング診断をおこなう場合、親にその生命与奪の一方的な権利があるのかどうかという問題も生じる。これは、従来考えられてきた権利−義務の双務関係が成立しない場合である。
したがって、まだ存在しない未来の人格の生存権を考慮する世代間倫理をふまえた「環境倫理」が通常の時間軸にある“通時的”なものであるのに対して、生死の定義における概念の吟味を行なう「生命倫理」は胎児として圧縮された時間軸において問題となる“共時的”なものである。
こうして、生命倫理の問題は、区切りが移動することで確定できない要因を含むとともに、双務的でない一方的な権利だけで成立するか否かという環境倫理が主要テーマとする世代間倫理の課題とも共通の根をもっている。
したがって現代人は、広い意味において、見えないけれど存在している人格やすべての生命とその生存権をも考慮した行動とライフスタイルを選択する義務があるといえる。そのために、厳格な区別を有する権利=義務の双務関係に依存しない生命倫理をも含んだ「環境倫理学」が必要である。つまり、生存権をめぐるすべての生命と生存権を保証する環境についての新しい論理と思考方法が求められるだろう。