- A. 人類史における環境問題
- 最近における地球規模の環境問題の顕現化もあって,人々の環境や環境問題に関する関心の度合いはいくらか高まりを見せているが、現実の環境は必ずしも改善されているとは言いがたい状況が続いている。それには後でふれるように環境とか環境問題のもつ本来的な性質が影響しているように思われる。
ところで、人類にとって環境問題は今に始まったわけではなく,その歴史において時代なり地域なりにさまざまな形で存在した。はじめのころは人間を取り巻く環境はほとんど自然的環境要素から成り立っていたが、時代が下がるにつれて人為的環境要素が多くなり、今日では後者のほうが大部分を占めるまでになっている。このことは従来、「進歩」というキーワードで当然の出来事として評価されていたが、「環境問題」という視点で捉え直すと違った評価が出来る。すなわち、もともと人間は他の生物と同様、現状に満足していれば、その環境を変えようとはしない「保守的」性質をもっているのではないか。環境を変えようとするのは、その環境に満足していない、言い換えれば何らかの環境問題が存在するからであろう。例えば、狩猟採取生活を営んでいた時代の人々が農業という技術を生みだし、生活スタイルを変えるようになったのには、人口増加などにともなう食べ物の不足という環境問題があったからであろう。古代のメソポタミア文明社会に見られた灌漑農業技術も湿潤・温暖から乾燥・寒冷へと地球規模の気候変動をきっかけに生じた食料不足という環境問題を解決するために生み出されたものである。これによって食料不足という環境問題は一時解決を見たが,やがて,塩害という新たな環境問題が生じ,その解決ができないまま,メソポタミヤ文明は崩壊した。
人類の歴史にはいろいろな文明の栄枯盛衰が見られたし、また地域ごとにさまざまな生活スタイル(「文化」と呼ぼう)が見られたり、現在でも存在しているが,こうした文明や文化はそれぞれその時代や地域が抱えていた環境問題の解決を目指した結果のものと言える。現在我々が享受している文明は17世紀に生まれた近代科学の知識を活用して開発された技術,いわゆる科学技術が生活の中に深くかかわり,近代科学のもつ実証精神などを思想的バックボーンにした文明である。その科学文明は我々に物的豊かさ,便利さ,快適さなどを与えてくれ、人々はそれを歓迎し、今日までそれを受け継いできている。しかし、今、その科学文明なるものが、必ずしも自分達を幸福にしてくれるとは限らないことに人々は気づきはじめたのである。
|
科学文明とは 科学的に考えることが「良いこと」 科学技術が生活の中に浸透 |
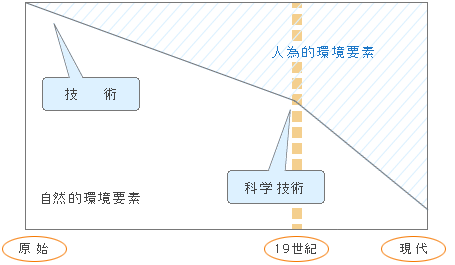
人間環境の変化
- B. 世界の環境問題
- 科学文明を担う科学技術は私達人類に物的豊かさを与えてくれた一方で,さまざまな環境問題を生じさせた。はじめのころは早くから工業化を目指した欧米の国々や我が国などいわゆる工業先進国と称する国々で大気汚染,水質汚濁などの地域的な環境問題を生じた。一方で,そうした科学技術の恩恵を受けないまま,先進国の資源供給の役割を担わせられた国々、いわゆる発展途上国では食料不足,森林などの乱開発,さらには先進国から出される産業廃棄物の処理によって生じる環境汚染など違った形の環境問題を抱えることになった。こうした環境間題における先進国と発展途上国の質の違いはそのまま両者の政治的経済的落差を示すものである。1972年のスウェーデンのストックホルムで開かれた国連人間環境会議ではこれ以上の資源やエネルギーの枯渇、環境悪化を危惧する先進国と、工業化を目指しそのための資源・エネルギーのさらなる使用や人口増加を求める発展途上国との間での対立が見られた。この構図は20年後の1992年にブラジルのリオで開かれた「環境と開発」をテーマにした地球サミットにおいても存在した。
1980年代になると国や地域を超えた地球規模の環境問題、例えばオゾン層の破壊,温暖化,あるいは酸性雨などがクローズアップされることになった。さらには、地球の各地で森林の減少や砂漠の拡大、土壌の流失、またそれらに関連しての野生生物種の減少などが見られるようになった。最近では人工化学物質の生態系への影響、とりわけ環境ホルモンといわれる化学物質による環境汚染、あるいはゴミ焼却などによって発生するダイオキシン汚染など新たな環境問題が生じている。
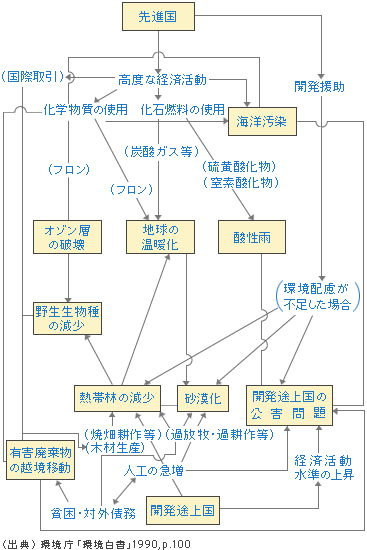
「問題群」としての地球環境問題
- C. 日本の環境問題
- 日本では,1960年代から顕現化してきた公害,特に水俣病,イタイイタイ病,四日市喘息などが大きな社会問題となった。1970年には公害を集中的に審議する国会が開催され,それまで各省庁がばらばらであった環境問題への取組みを一元化するために1971年には環境庁が発足した。このころには上記のような企業型公害の他に自動車の排気ガスにも含まれる窒素酸化物や炭化水素などが原因となる光化学スモッグが問題になり,企業ばかりでなく,生活者にも責任の一端がある環境問題が現れるようになった。
1980年代には洗剤による水質の汚れ,あるいは日々排出するゴミの増加など,ますます生活者側のかかわりが大きくなった環境問題が見られるようになり,環境庁は企業型公害から生活型公害への変化を強調するようになる。たしかにそうした傾向は見られるが,企業の責任が全く消えたわけでなく,環境を悪化させることを承知での生産活動が続けられているところもある。また,最近では産業廃棄物の処分の問題がクローズアップされている。海岸を埋め立てた処分場は限界に近づき,地方の山野の谷間が廃棄物処分場としてその役割を担わせられ始めている。さらにわが国でも環境ホルモンやダイオキシンの問題が注目されるようになっている。