- A. 自然環境を知る学習
- 環境教育の実践を見ると,さまざまなアプローチがあることが知られる。あるグループでは自然観察会を開くことに力を入れれば,別のグループでは空き缶回収活動に汗を流し,それこそが環境教育であると主張される。しかし,それらは環境教育の全体像のごく一部であることが多い。
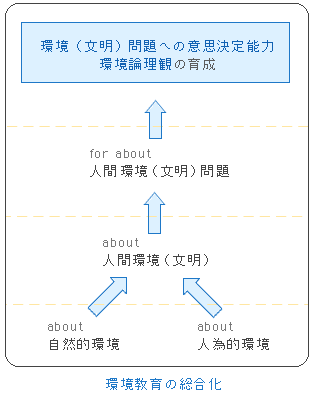
環境教育の全体像環境教育で学習対象としているのは前節の目的や目標からもわかるように人間環境や環境問題である。すでに述べたように人間環境には自然環境と人為環境とがある。したがって,環境教育の学習ではこの2つの環境を取り上げる必要がある。
自然環境とはいうまでもなく,人間とかかわりをもつ自然である。この場合自然について学習するのと,自然環境について学習するのでは意味が異なる。前者の場合には人間の活動や人間とのかかわりについて必ずしも触れる必要はない。たとえば,「川」という自然事象を取り上げてみよう。その川にどのような生き物が棲んでいるかとか,その川の水流の速さはどのくらいかなどを学習するとき,特に人間生活とのかかわりを考えなければ「自然について」学習したことになる。これに対して,その川の水を飲料水として使用していたり,逆に家庭から生活排水を流していたりしてかかわりをもったとき,その川はかかわりをもった人にとっての環境になり,その立場でその川についての学習,たとえば生活排水がその川の生態系にどのような影響を与えるかなどの学習をすれば「自然環境について」学習したことになる。
ところで,すでに述べたように自然環境にはいくつかのレベルがある。一番基本的なレベルとしては空気,水,土などの無機的な環境要素や他の生物たち。また,視点を変えるといろいろな形のエネルギー(光,熱,音など)も環境要素となる。次のレベルはこれらの環境要素が組み合わさったもの,たとえば川,海洋,森林,草原,砂漠,大気圏などが環境として存在する。さらに,それらが組み合わさって大陸が,そして地球全体が環境という視点で学習対象となる。したがって,自然環境についての学習というとき,どのレベルであるかを明確にしておく必要があろう。
- B. 人為環境を知る学習
- 人間の手が加わったものも私たちの周りに多く見られ,私たちとかかわりをもっているものが多い。というよりもほとんどがそうである。かかわりがあれば当然環境の仲間入りとなる。このグループを指して人為環境というのだが,この場合にもいくつかのレベルを考えることができる。
自然環境の場面に登場した無機的な環境要素のひとつ「水」も物質的には自然のものであるが,最近の水,特に飲料水は人間によって「加工」されている。この場合,人為環境要素と言うべきであろうか。同じことが空気についても言えそうである。いろいろな汚染物質が入り込んだ空気も人為環境要素の仲間(?)。また、とかく忘れられがちであるがさまざまに加工された食べ物も立派な人為的な環境要素である。
少しレベルを上げると川や森でも人間の手が加わったものがある。前者では三面コンクリート張りのものが思いだされる。後者では人工林(植林地)である。これらが環境教育での学習対象になったときは自然環境の学習をしているのでなく,人為環境の学習をしているということになろうか。現実には両者を明確に区別することはできない場合が多い。我が国の代表的な風景の田園を見て自然の豊かさを感じる人もいるが,それはあくまでも人為的なものであり,人間の管理が常に必要な状態である。そのようなものを半自然と呼び,自然環境と区別することがあるが,この半自然は環境教育にとって重要な学習対象である。
人為環境では家,街並み,都市などの視点もあり,タウン(街並み)・ウォッチングのような環境教育のプログラムも存在する。現在人類の大半が生活する都市は人為環境の典型であり,これについてよく知るということは,自然をよく知ることとともに大切なことである。
- C. 科学文明を知る学習
- これまで人間環境を自然環境と人為環境の2つに分けてきた。おそらく後者に属することになるであろうが,文化環境とか社会環境という言葉もしばしば使われる。さらには精神環境というように人間の内面からの見方もある。これらは環境教育の学習対象なのだろうか。前二者(文化環境,社会環境)は当然学習対象として取り上げられるべきものであろう。これに対して,精神環境は自然環境,人為環境の視点を変えたもの,言い換えるとこれらと並列に置かれるものではなく,自然環境や人為環境について学習する過程で問題として浮かび上がってくるものなので,あえて特別に取り出さなくても結果としては学習することになろう。
さて,重要なのは文化環境というか,大きくは文明というか,それらについての学習である。特に今日の環境問題の背景にあると言われる科学技術について,その特徴をよく知ることである。しばしば,科学技術が環境問題を生じさせたとして,その基礎にある科学自体をも否定する考えがあるが,その是否を問うためにも近代科学やそこから生まれた科学技術の特徴を明確にする必要がある。
17世紀に成立したと言われる近代科学は主として要素還元的方法を採用し,それによって一定の成果を収めた。物質が原子から成り立つこと、生命現象の基本単位は細胞であり、さらに遺伝情報を担う物質はDNAであることなどを明らかにし、私たちの物質観や生命観に大きく影響を与えた。また、ロケットを月にまで飛ばす技術の基礎となったニュートンの運動理論も要素還元的方法の成果である。しかし,この方法は要素間の関連性についての認識を不十分なものにし,そこから開発された技術によって,いろいろな環境問題を生じさせることになった。その意味からも環境教育において科学や科学技術の本質や特徴をしっかり学習する機会を与える必要がある。
最近では科学(science)と技術(technology)と社会(society)の関連性を考えさせる教育(いわゆるSTS教育)が注目されているが,この教育は上記のことからわかるように環境教育と重なるところが大きい。いずれの場合でも文明の問い直しにつながるものであり,そのためにはいずれにも歴史的視点を加える必要がある。筆者はこれらを総合したHNSTSE(History and Nature of Science and Technology in the Social Context and these Influence to Human Envvironment)教育を提唱する。