modern chinese economy
2-1. 経済建設の初期条件
担当:甲南大学 青木浩治 藤川清史
1949年の10月1日に中華人民共和国が誕生します。しかし、日中戦争と国共内戦のために、国土は疲弊していました。産業と呼べるのはわずかに以下の程度で,中国を総合的に見ると、産業はほとんどない状態でした。
| 上海 | :紡績工業・食品工業 |
| 天津・青島 | :紡績・食品が点在 |
| 南京 | :化学工業 |
| 鞍山 | :製鉄業 |
| 大連 | :化学工業 |
ただ、東北地域(旧満州国地域)にあった日本資本の工場や鉄道のいくらかは残存していました。
GDPシェアで見ると東北と上海で約3分の1、第二次産業に限ると東北と上海で約半分になります。所得配分は地域的に偏在していました。
図2-1は省別の製造業のDGPを昇順に並べ、縦軸にはその累積の100分比を見たものです。図の折れ線が45度線に近いほど省別のGDPが平等であることを意味します。
1952年での省別の分配は相当不平等でした。1978年での省別の分配は多少平等化しますが、それでも格差は大きいままです。グラフ中の一つの点が一つの省を表します。中国には33の省があるのですが、チベットと海南での工業GDPのデータがありませんので、点は31個あります。1952年では工業生産の上位6つの省で、1978年では上位7つの省で、中国の工業生産全体の50%を占めていました。
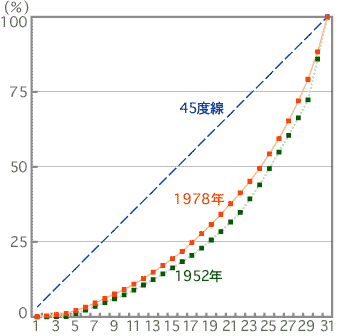 図2-1 製造業GDPの集中度
図2-1 製造業GDPの集中度
一人あたりのGDPを計算してみました。一人あたりのGDPの最も高い地域は上海です。
図2-2は、一人あたり製造業GDPの推移をいくつかの省についてグラフにしたものです。最も豊かな地域は上海で、その他の地域を大きく引き離しています。2位の北京(あるいは天津も北京と似ていますが)を2倍以上引き離しています。ついで、遼寧などの比較的工業の進んだ地域があり、その以外の省は遼寧以下に固まって存在します。このように、中国では一部の地域に生産力が偏在していました。中国政府は、産業化一般に取り組むことに加えて、地域の格差を小さくすることにも腐心せねばなりませんでした。
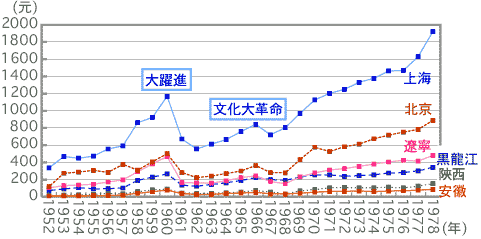 図2-2 一人あたり製造業GDPの推移
図2-2 一人あたり製造業GDPの推移
ところで、後からお話することなのですが、
図2-2では1960あたりピークがありその後工業生産が大きく落ち込んでいることに気づいたと思います。この時期は「大躍進」の時代といわれます。大躍進というのはそのスローガンで、実際には「大後退」になりました。なぜそのようなことになったのかは、次の第3章で詳しくみます。また、1966年ごろにも落ち込みが見られます。この時期に「文化大革命」と呼ばれる大衆運動がはじまっています。これも第4章で詳しく見ることにします。
グラフは1978年で終わっています。実は中国は1978年〜1979年を境にして、大きく変わりました。そこからは、この教材の後半の部分で詳しく検討したいと思います。1949年を「新中国」の誕生といますが、1978年は「現在中国」の誕生といえるでしょう。
ところで、
図2-1と
図2-2は名目の工業GDPを対象にしてきましたが、
図2-3には(1978年基準の)実質GDPの推移を示しました。ここでも、1960年(大躍進)と1966年(文化大革命)の時期にGDPの後退が見られます。日本の1960年代は戦後の復興から高度成長へ向かった時期でしたが、中国の1960年代はエンジンがかかり始めたら失速したという状況だったのです。
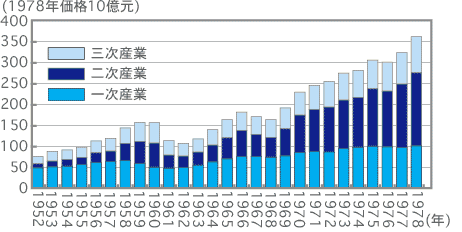 図2-3 実質GDPの推移
図2-3 実質GDPの推移
ついでに、
図2-4に就業者の産業別構成比の推移を示しておきました。1952年当時は全人口の90%が農民でした。そして、そのうち60%が飢餓ぎりぎりの水準だったといわれています。
これも後から触れますが、1958年には工業の就業者が急増しています。このため農業生産が停滞し、中国の食糧事情はますます悪化しました。
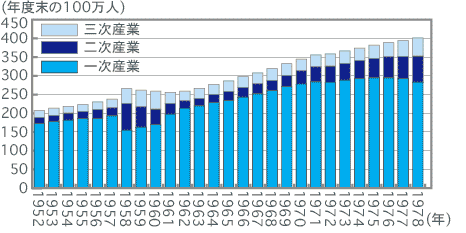 図2-4 産業別の就業者
図2-4 産業別の就業者