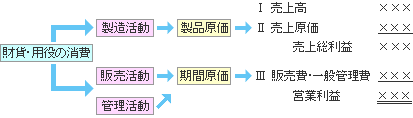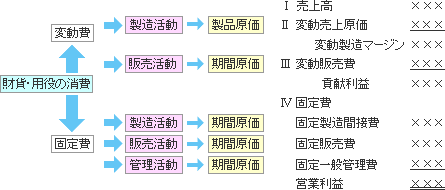(1)直接原価計算と全部原価計算による損益計算書
直接原価計算と全部原価計算との主な相違点は、製品に賦課する原価の違いにある。すなわち、全部原価計算では、製品原価の計算は全部の製造原価をもってなされる。
これにたいして、直接原価計算は、(1)製造原価だけでなく販売費や一般管理費を含め、原価を直接原価と期間原価に区分し、(2)売上高から直接原価を控除して貢献利益(または限界利益)を算出し、(3)さらに期間原価を控除して営業利益を計算する。
その違いを損益計算書で比較すると次のとおりである。
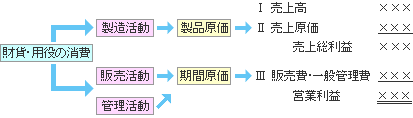
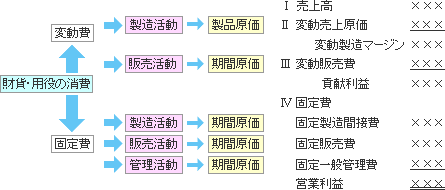
(2)直接原価計算の利益と全部原価計算の利益
直接原価計算の利益と全部原価計の利益とは、固定製造費を期間原価としてあつかうか否かによって、異なる。直接原価計算と全部原価計算の2つの損益計算書を比較すると,営業利益に関して次の違いが指摘できる。
- 直接原価計算では、利益は売上量の増減に応じて変動し、生産量の増減に直接関係しない。
- 売上量と生産量が等しく、在庫に変動がなければ、直接原価計算の利益と全部原価計算の利益は同額となる。
- 生産量が売上量を上回り在庫が増加するときは、全部原価計算の方が大きい利益を出す。
全部原価計算においては当期に発生した固定製造原価の一部が、期末棚卸資産に配賦され、その額だけ、当期の売上原価が少なくなるので、直接原価計算より利益が大きくなる。
- 売上量が生産量を上回り在庫が減少するときは、直接原価計算の方が大きい利益を出す。
全部原価計算においては、棚卸資産に含まれていた固定製造原価が当期の収益に課されるため、固定製造原価の額は、その期に発生した額よりも多くなる。よって、全部原価計算の利益は、直接原価計算より小さくなる。
- 両計算制度は長期的にみると、利益の差は小さくなる。
(3)直接原価計算による外部報告が認められない理由
直接原価計算にもとづく財務諸表は、制度会計上、外部報告として認められていない。それは、次のような理由による。
- 全部原価の原則に反する
全部原価計算では、完成品のうち当期売上品に含まれる固定製造費が売上高に対応されるため、期末仕掛品と期末製品中の固定製造費は次期に繰り延べられるのに対し、直接原価計算における固定製造費は、そのまま当期の期間費用として売上高に対応させられる。
制度会計上、原価計算は、財務諸表によって表示される真実な原価を集計する目的があり、原価計算基準では全部原価によって棚卸資産を計上することを原則としている。
したがって、直接原価計算の製品原価は変動製造原価のみで計算された部分原価であるため、この原則に反する。
- 原価の変動費と固定費の分解において恣意性が介入する
直接原価計算では、原価を変動費と固定費に分解することが必要となるが、この分解は一意的でないため製品原価計算に恣意性が介入し、制度会計になじまない。
(4)固定費の期末調整
直接原価計算による外部報告が認められていないため、直接原価計算を採用している企業においては、公表財務諸表を作成するにあたって、全部原価計算による数値に直すための調整計算が必要となる。これが固定費の期末調整の問題である。
これは、期末棚卸資産に含まれている固定費を計算することであり、期首と期末の棚卸資産に含まれる固定製造原価に差が生じるという原理を応用することによって、次の簡式でもとめることができる。
| 全部原価計による営業利益算 |
= |
直接原価計算による営業利益 |
+ |
全部原価計算による期末棚卸資産に含まれる固定製造費 |
− |
全部原価計算による期首棚卸資産に含まれる固定製造費 |
ただし、棚卸資産に含まれる固定製造費について、期首と期末の棚卸資産の増減を考慮しなければならない。
また、その計算の精粗によって、(1)一括法と(2)科目別調整法とがある。
- 一括法
原価差額を仕掛品、半製品、製品とに区分することなく、一括して期末資産に配賦する方法。
- 科目調整法
原価差額を、科目別に、さらには、評価法(先入先出法、後入先出法、平均法など)の相違を考慮して算定し、その結果をもとに、期末棚卸資産を計算する方法。