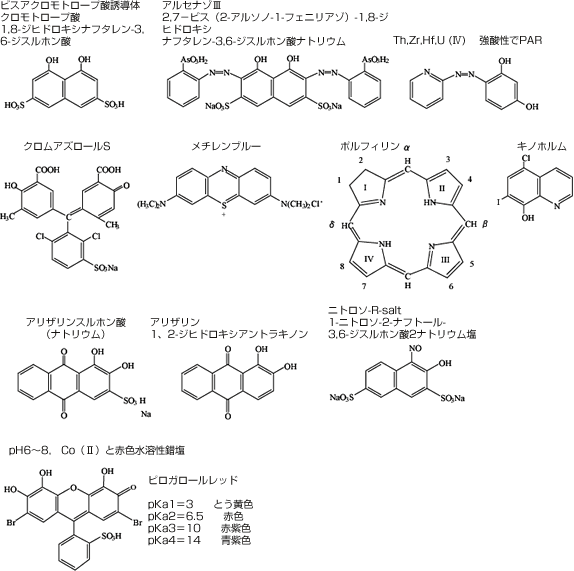式(2・7)におけるモル吸光係数

は呈色化学種の種類、波長、温度などによって定まる定数で、呈色化学種の面積吸収係数(ディメンション

)です。

が大きいほど呈色は強く(鋭敏に)なり、定量の感度は増加します。
いま、

の大きさについて考えると、

は呈色化学種の大きさ、正しくいえば光吸収に有効な断面積

と、電子遷移の確率

に支配されると考えられるので、

(2・8)
となります。ここで、

は比例定数で、9×103という値をもち、したがって

のとり得る最大値は、式(2・8)で

、

とすれば、約105となります。
実際に見出されている高感度発色試薬には、ビスアゾクロモトロープ酸誘導体(アルセナゾIII、カルボキシニトラゾなど)、ピリジルアゾ化合物(PARなど)、トリフェニルメタン誘導体(クロムアズロールSなど、第4級アンモニウム塩の共存下)、塩基性色素カチオン(メチレンブルーなど、イオン対を生成)などがあり、いずれもある種の金属イオンと10〜20万台の

をもつ錯体を生成します。(図2・8)また、ポルフィリン化合物は

が20〜50万台に達する錯体を生成し(図2・8)、最近多くの実用例が研究されています。この化合物では

が約

といわれています。
式(2・8)からわかるように、

を大きくするためには

と

がともに大きい方が効果的です。表2・5にはジピリジルおよびフェナントロリン誘導体の鉄(II)錯体について、配位子の構造と錯体の

値とを示したが、分子の大きさ(

と考えてよい)が増すほど

が大きくなる様子が定性的に理解できます。(図2・8)
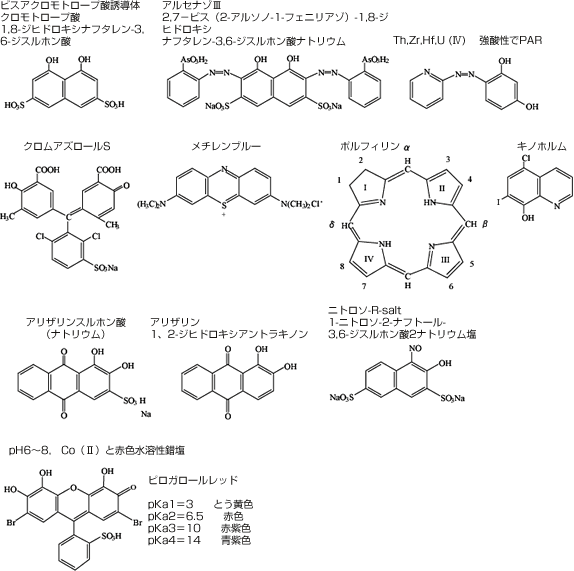
図2・8 高感度発色試薬の例
次に

についてごく簡単に触れると、一般に許容遷移(allowed transition)のときには

は大きく(およそ0.1〜1、

も1000以上)、禁制遷移(forbidden transition)のときには、

は小さくなります(およそ0.01以下、

は大体1000以下)。
金属錯体が電子スペクトルを生じるさいの遷移には、
- 遷移金属イオン内での励起による遷移(d-dまたはf-f遷移)、
- 配位子内の遷移、
- 金属から配位子(またはその逆)への電荷移動による遷移があります。
a)は多くの遷移金属イオン自身の呈色の原因となるもので禁制遷移であり、

は0.01以下、

は0.1〜100程度です。ただし

型
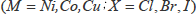
の化合物中には

が200〜1200のものもあります。b)は共役二重結合をもつ多くの有機発色試薬にみられるもので、

遷移に基づく許容遷移であり

は非常に大きくなります。また、

,

,

のような原子団は

遷移を示し、禁制遷移で

は比較的小さいです。なお、

,

などの呈色も

遷移によりますが

は1000以上です。c)は許容遷移で

が104にも達するものがあります。チオシアナト鉄(III)錯体、1,10-フェナントロリン鉄(II)錯体および銅(I)錯体などはこの例で、前者では

から

へ電子が移動して

基と

を生成し、後者では金属の

電子が配位子の

軌道へ移動します。