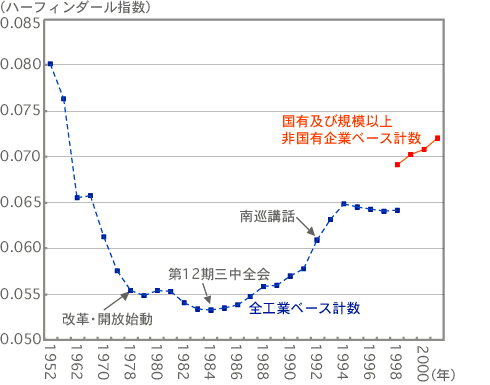modern chinese economy
6-1. 中国の成長モデル:双軌制
担当:甲南大学 青木浩治 藤川清史
6-1-1 双軌制
1984年10月の中国共産党第12期中央委員会第三回全体会議(通常、「中共12期三中全会」と略記されます)において「経済体制改革に関する決定」が行われます。この決定により、改革の重点が農村部から都市部へ移されていきました。その第一の柱は、従来、中央政府や所管官庁に属していた権限や利得を地方政府や国営企業に移譲する「放権譲利」であり、第二の柱は「双軌制(dual tracking systemもしくはtwo tier system)」と呼ばれる中国独特の市場経済化でした。簡単化して言うと、旧計画部門の改革はそこそこにしたまま「増量改革(新規分野を創出する改革)」を優先実行するというものです。
この路線の最大のメリットは、第一に計画部門を温存することで色濃く残る社会主義計画経済イデオロギーに対する防波堤を築けること、そして第二に市場経済部門を育成することにより、経済全体としてのパイを拡大できることでした。いきなり政治の民主化と国有・集団所有企業の民営化を進めて大失敗した旧東欧圏と異なり、中国経済は経済的縮小を経験していません(
表6-1)。漸進的かつ増量主義的路線を選択したからです。
| 表6-1 移行経済の経済復興度 |
| 中国 | 282 |
| ポーランド | 129 |
| ハンガリー | 112 |
| スロバキア | 110 |
| チェコ | 106 |
| ウズベキスタン | 105 |
| カザフスタン | 84 |
| ルーマニア | 84 |
| ロシア | 64 |
| ユーゴスラビア | 50 |
| ウクライナ | 46 |
|
|
注)
計数は1989年を100とした2001年時点での実質GDP。
中国は1978年を100とした1990年計数。
中国は1978-1990年、2001年は792。
資料)欧州復興開発銀行データ。
|
より具体的には、国営(ならびに都市集団所有制)企業が独占してきた、あるいは新規に発生した市場に郷鎮企業等の非国有部門の参入を認め、計画の枠外での自由競争を許容します。その自由市場で成立する価格が「市場調節価格」です。また、計画が主分野の価格が「政府固定価格」、そして政府関与のある分野の価格が「政府指導価格」です。このように同じ製品に複数の価格が付くわけで、こうした特長を捉えて双軌制を「価格双軌制」とか「多重価格システム」と呼ぶこともあります。
表6-2からも分かるように、価格自由化は1985年と1992年に著しく進行しています。そして、概ね90年代半ばにおいて自由化はほぼ完了しました。
| 表6-2 中国の三つの価格体系の割合 | 単位:% |
| |
年 |
1978 |
1984 |
1985 |
1988 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
| 小売商品 |
政府公定価格 |
97.0 |
73.5 |
47.0 |
30.0 |
29.8 |
20.9 |
5.9 |
4.8 |
7.2 |
8.8 |
| 政府指導価格 |
0.5 |
10.5 |
19.0 |
25.0 |
17.2 |
10.3 |
1.1 |
1.4 |
2.4 |
2.4 |
| 市場調節価格 |
2.5 |
16.0 |
34.0 |
45.0 |
53.0 |
68.8 |
93.0 |
93.8 |
90.4 |
88.8 |
 |
| 農副産品 |
政府公定価格 |
92.6 |
67.5 |
37.0 |
25.0 |
25.0 |
22.2 |
12.5 |
10.4 |
16.6 |
17.0 |
| 政府指導価格 |
1.8 |
14.4 |
23.0 |
23.0 |
23.4 |
20.0 |
5.7 |
2.1 |
4.1 |
4.4 |
| 市場調節価格 |
5.6 |
18.1 |
40.0 |
52.0 |
51.6 |
57.8 |
81.8 |
87.5 |
79.3 |
78.6 |
 |
| 生産財 |
政府公定価格 |
100.0 |
|
64.0 |
60.0 |
44.6 |
36.0 |
18.7 |
13.8 |
14.7 |
15.6 |
| 政府指導価格 |
|
|
23.0 |
|
19.0 |
18.3 |
7.5 |
5.1 |
5.3 |
6.5 |
| 市場調節価格 |
|
|
13.0 |
|
36.4 |
45.7 |
73.8 |
81.1 |
80.0 |
77.9 |
|
| 出所)大橋英夫「シリーズ現代中国経済5:経済の国際化」名古屋大学出版会、2003年、45ページ。生産財の1985年計数は中兼和津次「中国経済発展論」有斐閣、1999年、201ページによる。 |
しかし、双軌制には副作用がありました。その最大のものは「不正・腐敗」の横行です。実際、同じモノに異なった価格がついているのですから、お金儲けはいとも簡単です。官僚が発給する計画部門の割当(購入許可証という形式をとっていました)を獲得したものが勝ちです。安い公定価格で買って高い市場価格で売れば、巨額の利益が得られるのです。ですからその公定価格での購入権を発給できる官僚は、盛んに横流しを行います。これを「官倒」と言います。官は官僚の意味、倒とは「転がす」という意味ですので、和訳すれば官僚ブローカーとなります。これが改革・開放後中国におけるおそらく最初の「権銭交易(権力をお金で取引すること)」でしょう。そしてこの官僚による不正行為の横行が後に述べる天安門事件の温床となります。現在でも中国民衆に根深くある不満、つまり「不公正な蓄財」の時代が始まるのです。
6-1-3 諸侯経済
80年代後半はまた、中国経済が混乱した時期でもあります。その一つが「地域保護主義」の台頭です。
図6-1は工業部門(鉱業、製造業、電力・ガス・水道)が中国の地域間でどの程度集中しているかを指標化したものです。ここで図の計数が低下(上昇)すれば工業が地域間で分散化(集中化)していると読みます。グラフからも分かるように、1978年以前の計画期では中国の工業部門は一貫して地方分散化の傾向を示していました。これは毛沢東の指導理念の下で「大而全、小而全(大も小も全てを持つという意味、中国版ワンセット主義のこと)」が追求され、あらゆる地域で完結した自給自足経済が追及された結果であると言われています。その典型例が鉄鋼産業、そして自動車産業でした。しかし、この傾向は改革・開放が始動した80年代でも持続していることに注目して下さい。つまり、規制緩和の下、80年代においても中国全域において新しい産業が横並びで創設されたのです。
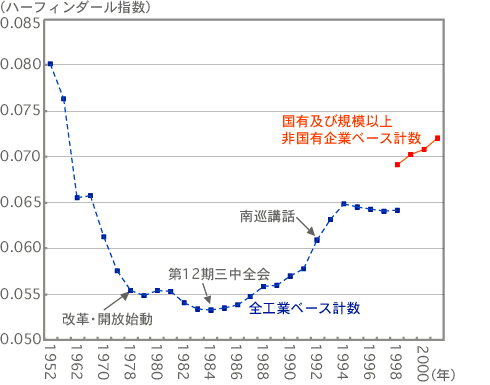 図6-1 中国の工業部門地域集中度
図6-1 中国の工業部門地域集中度
注)
図の計数は30省・市の工業部門シェア(対全国比、1952・57年はチベットを除く)の自乗を合計したもの(ハーフィンダール指数と言う)。この比率が低下(上昇)したとき、工業部門は各地域へ分散化(集中化)したことを意味する。1998年以前は全工業企業ベース、それ以後は全国有工業企業及び年商500万元以上非国有工業企業ベース計数。

資料)
国家統計局国民経済総合統計司編「新中国五十年統計資料匯編」1999年、国家統計局編「中国統計年鑑」1999-2002年。 |
こうした横並び投資の最中、原油やジュート、カイコといった資材の争奪戦(「マユ大戦」、「原油大戦」、「ジュート大戦」等と呼ばれています)、域外製品の流入阻止といったあからさまな貿易規制が広範化していきます。このさながら国家間の貿易戦争のようなことが中国国内において蔓延し、自由な国内交易を阻害する動きが台頭しました。この現象を「地域保護主義」とか「諸侯経済」と呼んでいます。
勿論こうした貿易規制強化は、経済学の教科書が教えるように国内交易そのものを萎縮させるだけで、逆効果です。ですから中央政府もこうした地域保護主義を規制する態度に出ました。そのためさすがに超法規手段による地域保護現象は表舞台から消えましたが、中には自動車のような陰湿なケースも残っているようです。
しかし、このような「市場分断化」現象は、90年代に入って次第に薄れつつあります(
図6-1)。その典型例が家電産業であり、次の
表6-3が示しているように、広東省等の特定の地域に生産が集約化しています。高度経済成長期の日本と同じように、中国においても生産集積が進行し始めていると考えてよいでしょう。
| 表6-3 家電製品の省・市別生産シェア(上位10省・市) | 単位:% |
| テレビ |
冷蔵庫 |
洗濯機 |
| 1988年 |
2001年 |
1988年 |
2001年 |
1988年 |
2001年 |
| 上海 |
18.9 |
広東 |
38.9 |
広東 |
18.0 |
山東 |
26.5 |
上海 |
16.9 |
山東 |
23.4 |
| 江蘇 |
17.4 |
四川 |
13.7 |
浙江 |
15.6 |
広東 |
20.9 |
広東 |
15.2 |
浙江 |
17.3 |
| 広東 |
11.1 |
遼寧 |
9.2 |
江蘇 |
8.8 |
安徽 |
13.9 |
浙江 |
11.3 |
江蘇 |
17.2 |
| 四川 |
5.8 |
山東 |
9.1 |
上海 |
7.6 |
江蘇 |
11.6 |
遼寧 |
8.3 |
広東 |
13.5 |
| 天津 |
5.4 |
江蘇 |
7.8 |
四川 |
7.4 |
河南 |
7.7 |
山東 |
6.5 |
安徽 |
8.5 |
| 遼寧 |
5.0 |
安徽 |
5.5 |
湖南 |
5.2 |
湖南 |
3.5 |
四川 |
6.1 |
上海 |
5.6 |
| 福建 |
4.6 |
福建 |
4.3 |
遼寧 |
5.0 |
上海 |
3.2 |
北京 |
5.5 |
湖北 |
4.8 |
| 浙江 |
4.2 |
上海 |
2.7 |
天津 |
4.4 |
貴州 |
2.8 |
湖北 |
5.5 |
山西 |
2.0 |
| 陜西 |
3.7 |
河南 |
2.5 |
北京 |
3.1 |
江西 |
2.5 |
甘粛 |
4.1 |
四川 |
1.8 |
| 北京 |
3.7 |
天津 |
1.3 |
貴州 |
2.9 |
陜西 |
2.2 |
吉林 |
3.3 |
甘粛 |
1.6 |
 |
| 合計 |
79.8 |
|
94.9 |
|
78.0 |
|
94.9 |
|
82.9 |
|
95.9 |
|
注)テレビは白黒合計(2001年はカラーTVのみ)。
資料)国家統計局編「中国統計年鑑」1989・2002年。
|