modern chinese economy
6-3. 中国の新しい成長メカニズム
:「大衆消費者社会」モデルの出現
担当:甲南大学 青木浩治 藤川清史
6-3-1 普及の波
6-3-2 分配構造の変化
もっとも日本と異なり、中国の大衆消費社会は都市化を軸として出現したわけではありません。都市への人口流入は戸籍制度によって厳しく制限されているからです。しかし、中国は都市部といえども日本の人口を上回る巨大な人口大国であり、都市部の購買力だけでも相当額の需要は喚起可能です。
こうした都市部の旺盛な消費を支えた一因は、計画期に低く押さえられていた国営企業労働者の分配率改善でした。既に説明したように、計画の時代には農産物・原材料価格を人為的に抑制し、加工品価格を割高に設定することによってそのマージンを工商税(流通税)や国営企業の利潤上納という形で強制貯蓄させ、重点分野である重工業セクターの資本蓄積に充当していました(「価格鋏状効果」と言います)。ところが、強制貯蓄は昇給の実質的停止等の形で都市部の労働者にも強要されており、その大きさは1964-1978年平均でGDPの10.4%にのぼっていたようです。ちなみにこれは同期間の投資の3分の2に相当する大きさです。
しかし、1978年の改革・開放政策転換を端緒として、労働者の取り分が改善されていきます。まず改革・開放初期において、それまでほとんど実施されていなかった昇給が再開されます。そしてこの賃上げは1984年から加速化しました。第二に、国営企業に対する「放権譲利(経営や分配の決定権限を政府・所轄官庁から経営者に移譲すること)」政策の一環として、1984年頃から留保した利潤を従業員のボーナスとして支給してよいことになりました。なお、1984年に国営企業の利潤上納制度は廃止され、所得税納税方式に変更されています(「利改税」と言います)。その結果として、国営企業の労働者の取り分は顕著に改善され(
図6-5)、これが都市部の旺盛な消費需要を支えたのです。もっとも分配率改善が、その後行き過ぎてしまうのですが。
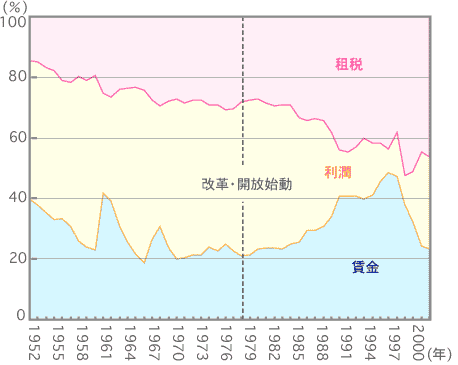 図6-5 国有工業企業の分配率(%)
図6-5 国有工業企業の分配率(%)
注)
賃金、利潤、納税額合計に占める各項目の構成比。図の労働者の取り分は利潤からのボーナス分が無視されているので、過小評価されている。また、租税には一部付加価値に含まれないものがある。

資料)
国家統計局工業交通統計司編「中国工業経済統計年鑑」各年版。 |