modern chinese economy
7-1. 鄧小平の南巡講話と貿易・外資ブーム
担当:甲南大学 青木浩治 藤川清史
7-1-1 南巡講話
1992年1月から2月の春節を挟む期間、実質的指導者である鄧小平は中国の南部地域を視察して回り、同時に不毛なイデオロギー論争を止めて「改革・開放へ邁進すべき」との講話を行いました。世に言う「南巡講話」です。そして同年10月の中国共産党第14回党大会において「社会主義市場経済」路線が確定します。これによって中国は「計画か市場か」の長いイデオロギー論争に終止符を打ち、以後、「中国的特長を持った市場経済」の建設に邁進することになるのです。
7-1-2 直接投資ブーム
この南巡講話をきっかけに、ブームが再来します。これまでのような消費ブームではなく、今度は「開発区ブーム」、「直接投資ブーム」でした。
図7-1は、中国に対する直接投資の契約額(棒グラフ)と実際の実行額(折れ線グラフ)を示したものです。この図によると、90年代初頭までは比較的低調であった海外からの投資が1992年より飛躍的に増加し、近年、再び増加に転じていることが分かります。実はこの中国に対する外国からの直接投資(企業進出に伴う出資や子会社に対する貸付け、留保利益の再投資)が、90年代以降の中国の成長をリードする牽引車の役割を果たすことになるのです。
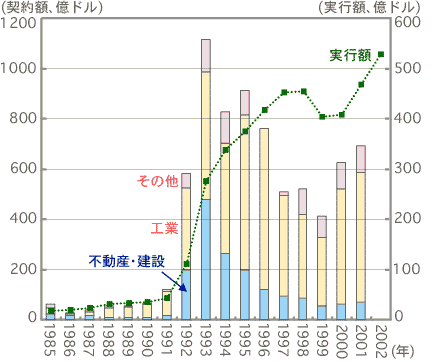 図7-1 中国の対内直接投資
資料)国家統計局編「中国統計年鑑」各年版。
図7-1 中国の対内直接投資
資料)国家統計局編「中国統計年鑑」各年版。
その背後には次のような政策変化がありました。
(1) 全方位・多元的対外開放の展開
90年代初頭まで、中国の外資誘致は基本的に特定都市もしくは地域に限定されていたという意味で、国内経済から意識的に開放区を「隔離」する方式を採用していました。その結果として広東・福建省といった特定の地域を除いて外資の重要度は低く、例えば1990年時点における工業生産に占める外資系企業生産額の割合は僅か1.8%でしかありませんでした。
しかし、南巡講話を契機に、中国はこうした対外開放区を大幅に拡大し、1992-94年時点において国家級の経済技術開発区を新規認可、長江沿岸の5都市(沿辺)、内陸15省都の空港を持つ都市(沿空)、4つの辺境都市(辺境)を開放都市に指定等、「全方位・多元的対外開放」へ転じたのです(
図7-2)。
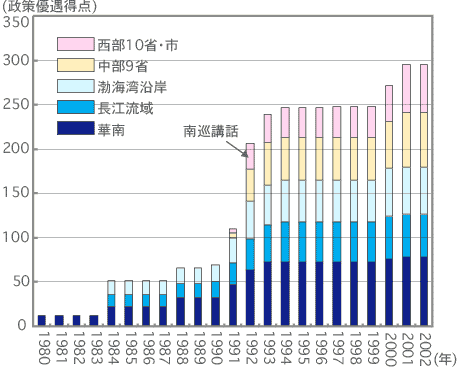 図7-2 中国の対外開放
図7-2 中国の対外開放
注)
経済特区は3点、経済技術開発区・台湾投資区・辺境経済合作区は2点、その他国家級開放区は1点と勘定した。図はその地域別得点分布を表す。

資料)
大橋英夫「シリーズ現代中国経済5:経済の国際化」名古屋大学出版会、2003年、18-19ページ、および対外貿易経済合作部ホームページより作成した。
|
第二の要因は地方政府による積極的な外資誘致です。すなわち、南巡講話をきっかけに全国各地の地方政府は地域経済活性化の切り札として外資誘致競争を始めました。なにせ横並び(中国語で「攀比(パンビ)」と言います)での誘致競争であり、中には計画の中身もないうちに土地使用権売却に走る自治体も多かったようです。
しかし、土地がらみの開発となると、お隣の香港が本家本元であり、彼らがその機会を見逃すわけがありません。1992年からの外資ブームはまずこれら不動産・建設関連に集中するのです(
図7-1)。
第三の要因は、1992年に「以市場換技術(市場を技術と交換する)」政策が公にされたことでした。当時の中国の外資認可基準は原則として「輸出」か「先進技術」です。そしてハイテク産業に関しては、中国国内で生産された製品を中国国内市場で販売することが可能です。そしてこの1992年の「以市場換技術」政策により、「先進技術」の解釈を緩めて外資に国内での販売を可能にしていきます。
表7-1は在中国外資系工業企業の生産額に対する同輸出額の割合を計算したものです。この表によると、加工貿易狙いの進出を反映して80年代後半から外資系企業の輸出比率が上昇し、90年代初頭ではそれは90%を上回っていました。しかし1992年より、在中国外資系企業の軸足が輸出から国内販売に大きくシフトしたことが分かります。
| 表7-1 在中国外資系企業の輸出依存度 | (単位:%) |
| 年 | 輸出依存度 | 年 | 輸出依存度 |
| 1986 | 52.7 | 1994 | 45.0 |
| 1987 | 62.7 | 1995 | 40.5 |
| 1988 | 65.3 | 1996 | 42.2 |
| 1989 | 85.5 | 1997 | 43.1 |
| 1990 | 91.1 | 1998 | 40.0 |
| 1991 | 98.4 | 1999 | 38.7 |
| 1992 | 53.5 | 2000 | 42.1 |
| 1993 | 56.4 | 2001 | 41.6 |
|
注)
輸出を工業生産額で割った比率。1986-93年の為替レートは世銀の実効レート、その他は公定為替レートを使用した。外資系企業は在外華僑・華人系企業を含む。

資料)
国家統計局工業交通統計司編「中国工業経済統計年鑑」1988-2002年、国家統計局貿易外経統計司編「中国対外経済統計年鑑」2000年、国家統計局編「中国統計年鑑」2002年。 |
第四の要因として、近隣諸国・地域との国交関係樹立を指摘できます。具体的には1991年にシンガポールと、1992年には韓国と国交を樹立しました。また香港に続く第二位の投資国である台湾との関係改善も重要です。実際、1987年に大陸中国への墓参解禁、1991年には第三国経由での直接投資が解禁されました。
しかし、1992年以降の内陸部の開放により若干改善されたものの、直接投資の東部偏在という現象は依然、続いています(
表7-2)。確かに投資先は80年代の広東・福建省から、90年代では上海・江蘇省の長江流域地域へシフトしていますが、それでも東部沿海省への投資偏在は変わっていません。なによりもインフラの欠乏、市場の欠乏、そしてながらく続いた政策上の東部優遇・内陸部冷遇等がその主要原因です。
ただし、2001年よりスタートした第10次五ヶ年計画において、西部大開発に重点が置かれるようになりました。その一環として内陸部への投資誘導を狙った新たな政策が出されています(2001年に12の国家級経済技術開発区が、主として内陸部を中心として認可されました)。
表7-2 中国の対内直接投資地域分布:累積投資額の地域別構成比(単位:%)
| 年 |
1980 |
1985 |
1990 |
1995 |
2000 |
| 東部 |
99.0 |
94.4 |
93.0 |
87.6 |
87.8 |
| 渤海湾地域 |
1.7 |
12.4 |
23.0 |
20.3 |
20.7 |
| 長江流域地域 |
0.0 |
7.1 |
14.7 |
24.7 |
26.6 |
| 華南地域 |
97.4 |
74.8 |
55.3 |
42.6 |
40.5 |
| 中部 |
0.0 |
2.8 |
3.8 |
8.4 |
9.3 |
| 西部 |
1.0 |
2.8 |
3.2 |
4.0 |
2.9 |
|
注)
渤海湾流域=北京・天津・河北・遼寧・山東、長江流域=上海・江蘇・浙江、華南=福建・広東・広西・海南。

資料)
国家統計局国民経済総合統計司編「新中国五十年統計資料匯編」1999年、国家統計局編「中国統計年鑑」1999-2001年。 |
単純なお金の国際間移動と異なり、直接投資には新しい経営管理手法や生産技術といった、中国の最も不足している「経営資源」が伴います。しかも外資系企業で働いていた従業員がスピン・オフして新しい企業を立ち上げることも稀ではありません。このように直接投資は中国にとって新たな資本蓄積をもたらすだけでなく、「新しい技術」をもたらしくれます。ですから外資流入の有無は当該地域経済に非常に大きな影響を及ぼすことになるのです。
図7-3はこうした資本蓄積や新しい技術の導入を考慮した上で、どの程度外資が中国各地域の成長に貢献しているかを図示したものです。明らかに、外資がたくさん入ってくる広東・福建・江蘇省等では外資の成長加速効果が大きく現れ、逆に外資流入の少ない内陸部ではその寄与は小さくなっています。このように中国の地域経済成長に対し、外資は非常に大きな影響をもたらしてきたことは間違いないようです。
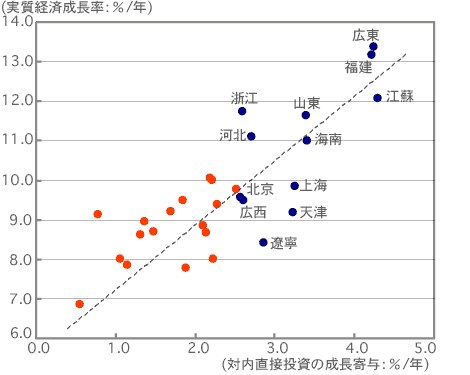 図7-3 中国の省・市別実質経済成長率と直接投資の成長率寄与:1986-2000年
図7-3 中国の省・市別実質経済成長率と直接投資の成長率寄与:1986-2000年
資料)
国家統計局国民経済総合統計司編「新中国五十年統計資料匯編」1999年、国家統計局編「中国統計年鑑」1999-2001年、その他から推計。
|
第二に、中国は1994年から輸出ブームに沸きます(
図7-4)。改革・開放後、中国の貿易は徐々に増加していましたが、1988-93年、1994年以降と、そのテンポが加速化します。
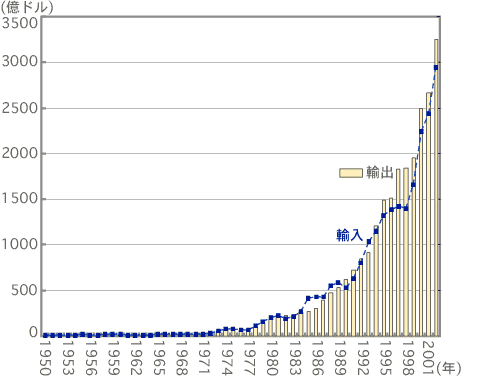 図7-4 中国の貿易
図7-4 中国の貿易
資料)
国家統計局国民経済総合統計司編「新中国五十年統計資料匯編」1999年、国家統計局編「中国統計年鑑」1999-2002年。
|
既に説明したように計画期は基本的に自力更生であり、貿易は従、しかも国家外貿企業による独占でした。しかし1978年の改革・開放を契機に、中国はアジアNIEsと同じように貿易を促進する政策に転じます。その後貿易は加速度的に拡大し、輸出は1978年の97.5億ドルから2002年には3255.7億ドルへと33倍以上に、輸入は108.9億ドルから2952.2億ドルへと27倍も増加します。また輸出世界ランキングも、1980年の26位から2003年に5位に躍進しました。
この貿易拡大の立役者は一つに既に述べた郷鎮企業ですが、90年代では外資系企業の役割が非常に大きくなります。また、中国の貿易は、大きく「一般貿易」と「加工貿易(来料加工、進料加工、来件装配、補償貿易)」に大別されますが、なかでも後者の加工貿易が中国の貿易拡大の推進力です(
表7-3)。
| 表7-3 中国の貿易形態別・所有制別貿易構成比(2001年)(単位:%) |
| 輸出 | 合計 | 国有企業 | 外資系企業 | 集体企業 | 私営企業 | その他 |
| 合計 | 100.0 | 42.5 | 50.1 |
5.3 | 2.0 | 0.1 |
| 一般貿易 | 42.0 | 27.6 | 9.0 |
3.6 | 1.7 | 0.0 |
| 加工貿易 | 57.1 | 14.2 | 41.0 |
1.7 | 0.2 | |
| 補償貿易 | 0.0 | 0.0 | |
| | |
| 来料加工 | 15.9 | 9.8 | 5.4 |
0.7 | 0.0 | |
| 進料加工 | 39.5 | 3.7 | 34.7 |
1.0 | 0.2 | |
| その他 | 0.9 | 0.7 | 0.0 |
0.1 | 0.1 | 0.0 |
 |
| 輸入 | 合計 | 国有企業 | 外資系企業 | 集体企業 | 私営企業 |
その他 |
| 合計 | 100.0 | 42.5 | 51.7 |
3.3 | 1.4 | 1.1 |
| 一般貿易 | 46.6 | 30.5 | 12.5 |
2.1 | 0.9 | 0.7 |
| 加工貿易 | 50.8 | 10.3 | 39.0 |
1.1 | 0.3 | |
| 補償貿易 | 0.0 | 0.0 | |
| | |
| 来料加工 | 11.9 | 6.9 | 4.4 |
0.5 | 0.0 | |
| 進料加工 | 26.7 | 1.8 | 24.4 |
0.4 | 0.1 | 0.0 |
| その他 | 2.6 | 1.7 | 0.2 |
0.1 | 0.2 | 0.3 |
|
注)
計数は全輸出(入)に占める構成比。加工貿易の輸出は補償貿易、来料加工、進料加工、保税貿易、輸入は補償貿易、来料加工、進料加工、保税貿易、加工貿易輸入設備、外資系企業原料設備輸入とした。外資系企業には在外華僑・華人系企業を含む。

資料)
中華人民共和国海関総署編「中国海関統計」2001年。 |
他方、
表7-4は、外資系企業の貿易が中国全体としての貿易にどの程度のウェイトを持っているかを年別・地域別に整理したものです。この表を観察すると、外資系企業の貿易シェアは2001年時点で輸出が50.1%、輸入が51.7%とほぼ半分となっています。そして驚かされるのは貿易増加、特に輸出増加に対する外資系企業の寄与度の高さです。特に1995-2001年の期間において中国の輸出増加のうち、実に73.6%は外資系企業の輸出増加によっており、これはマレーシアやフィリピンと大差ありません。少なくとも90年代後半からの中国の貿易拡大は、圧倒的に外資系企業によって牽引されてきたと言えるでしょう。
| 表7-4 中国の輸出に対する外資系企業輸出の寄与度 | 単位:% |
| |
外資系企業シェア(%) |
期間増加寄与度(%) |
| 1992年 |
2001年 |
1992-2001年 |
1995-2001年 |
| 輸出 |
全国 |
20.4 |
50.1 |
63.9 |
73.6 |
| 東部 |
21.2 |
51.3 |
65.1 |
74.4 |
| 渤海 |
12.3 |
54.6 |
72.5 |
93.2 |
| 長江 |
14.9 |
49.3 |
57.7 |
64.5 |
| 華南 |
32.4 |
56.1 |
69.0 |
77.6 |
| 中部 |
2.2 |
16.1 |
50.7 |
57.8 |
| 西部 |
3.1 |
10.0 |
15.8 |
26.4 |
 |
| 輸入 |
全国 |
32.7 |
51.7 |
61.0 |
56.4 |
| 東部 |
33.6 |
52.9 |
62.3 |
57.1 |
| 渤海 |
24.4 |
47.2 |
55.4 |
58.5 |
| 長江 |
29.2 |
60.3 |
68.6 |
62.8 |
| 華南 |
42.0 |
54.2 |
63.0 |
51.5 |
| 中部 |
14.7 |
27.2 |
42.8 |
24.0 |
| 西部 |
12.0 |
14.7 |
16.8 |
10.8 |
|
注)
渤海湾流域=北京・天津・河北・遼寧・山東、長江流域=上海・江蘇・浙江、
華南=福建・広東・広西・海南。地域別貿易額は原産地・仕向け地ベース。

資料)
国家統計局編「中国統計年鑑」1994/2002年。
|