modern chinese economy
12-5. 東アジアをめぐる新しい「国際経済循環」
担当:甲南大学 青木浩治 藤川清史
12-5-1 対米輸出低迷下の中国の躍進
次に、「人民元が実質米ドル・ペッグであるため、近隣の東アジアは迷惑を被っている」という議論について解説しておきましょう。具体的には東アジアにはアジア危機以後、変動相場制ないしそれに近い為替レート制度へ移行した国が増加しました。そのためこうした国々の通貨が米ドルに対して増価したとき、米ドルにペッグしている中国元に対しても増価するため、輸出が中国に一部食われてしまうという懸念があります。だから日本ばかりか韓国や東南アジアからも人民元の切り上げや変動幅拡大要求がでるのです(再度、
図12-4を参照して下さい)。
しかし、果たして中国は悪者なのでしょうか。この点を考えるためには2002年以降の国際経済の展開を考える必要があります。その第一のポイントは東アジアにとって生命線である対米輸出の動向です。
図12-6はアメリカの国別輸入動向を図示したものですが、特に2000年以降に注目して下さい。この図によると(1)1999・2000年のITブームによる対米輸出増加の後、日本、アジアNIEsの対米輸出は低迷している、(2)その中にあって中国(香港特別行政区を含む)の対米輸出は顕著に増加しており、2002年に日本を上回っている、ことが分かります。ちなみに(1)のポイントはその他の国も似たりよったりで、図示されてはいませんが東南アジアの対米輸出も2000年以降低迷していることに注意して下さい。このように近年の中国は、ジャーナリスティックに表現すると「一人勝ち」の様相を呈しているのです。
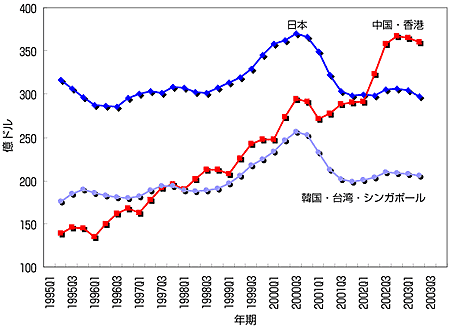 図12-6 アメリカの国別輸入(億ドル、季節調整値の三期移動平均)
図12-6 アメリカの国別輸入(億ドル、季節調整値の三期移動平均)
中国の対米輸出が増加している理由は比較的簡単です。特に2001年末の中国のWTO加盟は対中直接投資の増加と加工貿易の拡大をもたらしました。実際中国の貿易を牽引するのは実態的には中国に進出した外資系企業であり、例えば中国の最大の輸出産業に成長した電子産業では、全生産額の54%、輸出の79%が外資系企業によって担われています(2001年計数)。また、1995年以降の中国の輸出増加のうち4分の3は外資系企業によって牽引されました。このように中国を見る場合、”made in China”と”made by China”を区別して考える必要性があり、例えば「中国の台頭」と言った場合、かなりの程度「中国に立地する外資系企業の国際プレゼンスの拡大」と言ったほうがより正確であるかもしれません。こうした環境下にあってのドル安は、さらに中国への企業進出シフトと中国製品の躍進をもたらすのではないかとの懸念はもっともでしょう。
ところが事態はそう簡単ではないのです。その最も分かりやすい例が韓国です。次の
図12-7は韓国の国別輸出動向を図示したものですが、おどろくべきことに韓国の対中国輸出は、日本はおろか、2002年において従来最大の輸出先であったアメリカをも上回っています。台湾は以前からそうなのですが、実は東南アジア諸国でさえ中国向け輸出が近年顕著に増加しており、すでにシンガポール、マレーシアでは対中国向け輸出が対日輸出を上回っています。そしてこのまま行きますと、そう遠くない将来においてアメリカ向け輸出をも凌駕しそうな勢いなのです(
表12-2)。もちろんその背後には東南アジアや中国に進出した外資系企業の存在があります。
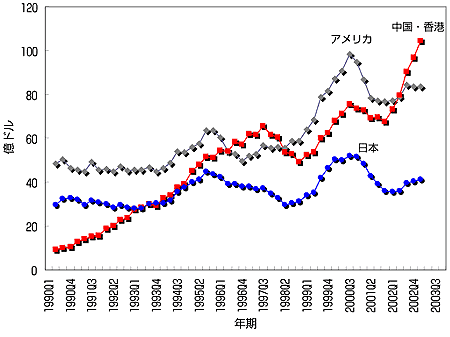 図12-7 韓国の輸出先別輸出動向(億ドル、三期移動平均)
図12-7 韓国の輸出先別輸出動向(億ドル、三期移動平均)
表12-2 日本・東アジア7ヶ国の貿易
| |
2002年輸出(億ドル) |
2000-2002年輸出伸び率 |
| 対米 |
対日 |
対中国・香港 |
対米 |
対日 |
対中国・香港 |
| 日本 |
1186 |
|
649 |
▲8.9% |
|
6.0% |
| 東アジア7 |
1334 |
747 |
1078 |
▲6.0% |
▲9.1% |
5.2% |
| |
2002年輸入(億ドル) |
2000-2002年貿易収支(億ドル) |
| 対米 |
対日 |
対中国・香港 |
対米 |
対日 |
対中国・香港 |
| 日本 |
576 |
|
629 |
609 |
|
20 |
| 東アジア7 |
1043 |
1155 |
515 |
465 |
▲408 |
563 |
| 注) | ▲はマイナス。東アジア7ヶ国は韓国・台湾・シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン。 |
| 資料) | ADB, Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries, 2003.その他。 |
このように為替レート変動の影響は、その直接的効果だけを観察していたのでは不十分であり、その間接効果も考慮しないとダメだということがお分かり頂けたのではないでしょうか。ポイントは1985-95年の執拗な円高・ドル安が日本の輸出に及ぼした影響と同じです。実際、その中身は変わりましたが、日本の輸出は円高期においてもあまり減っていません。アメリカや欧州向けは低迷気味でしたが、東アジア向け輸出が好調だったからです(
図12-8)。
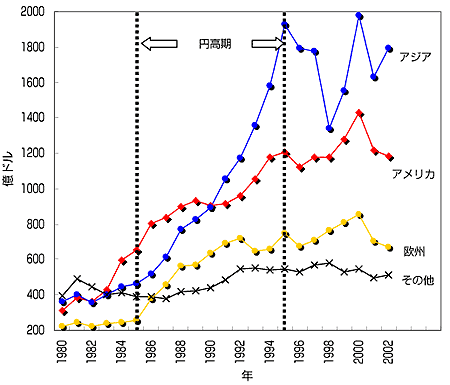 図12-8 日本の地域別輸出金額(億ドル)
図12-8 日本の地域別輸出金額(億ドル)
具体的に言うと、当時の東アジアは現在の中国と同じく「実質的な米ドル・ペッグ」制を採用していました。そのため円高・ドル安は同時に東アジア通貨に対しても円高が進行したのです。またこれが1985-1995年の10年間における東アジアの成長を促した基本的仕組みでした。そのため、円高・ドル安は東アジアの高度経済成長をもたらし、逆に日本の対東アジア向け輸出を増加させることになったのです。
このように考えると、現在の中国の実質米ドル・ペッグ制が変動相場制もしくはそれに近い相場制度を採用している国に対しても必ずしも悪影響を及ぼしているわけではないことが分かります。実際、日本を含む東アジア各国の地域別・国別輸出動向を観察すると中国・香港向けがダントツの伸びを示しており、日米向け輸出はパッとしていません(全出の
表12-2を参照)。このように中国は他の東アジア諸国に対して低迷する日米欧向け輸出を補う役割を果たしつつあり、その仕掛けが対中企業進出と加工貿易の拡大なのです。ですから人民元切り上げはこの新しい国際経済循環の芽を潰してしまう可能性があるわけで、中国の人民元切り上げの評価はこうした大きな枠組みで考える必要があります。もちろんこの新しい成長の芽を育む上でもう一つ重要な要素は、安定した「中米関係」「安定した中国と日本・東アジアの関係」です。