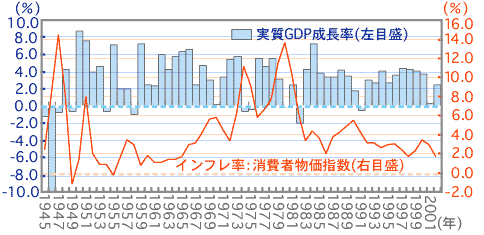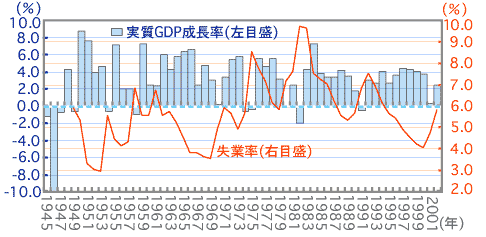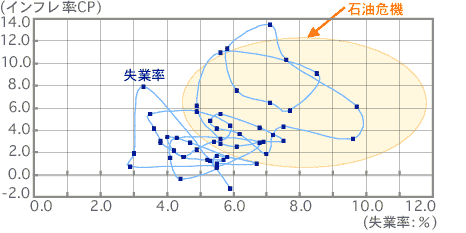modern american economy
1-1. 失業とインフレ
担当:甲南大学 稲田義久
戦後のアメリカ経済の動態を理解するため、ここでは3つの図を掲げました。1番目の図は経済成長率とインフレ率の関係を見たものです。2番目の図は経済成長率と失業率の関係を示しています。最後の図はいわゆるフィリップス曲線と呼ばれる、インフレ率と失業率の関係を見たものです。
経済(実質GDP)成長率で見ると、アメリカ経済は戦後直後(平時経済への移行期)の混乱期を経て、1950‐60年代には比較的高い成長率を実現しています。消費者物価指数(CPI)で測ったインフレ率をみると、戦後直後は戦争で蓄積していた潜在需要の爆発によりインフレに見舞われます。しかし、50年代には落ち着きを取り戻し、60年代はむしろ緩やかながらインフレが加速してまいります。好景気に支えられ失業率は急速に低下します。50‐60年代は高い経済成長、低い失業率、そして比較的緩やかなインフレを実現できたということで、この時代をアメリカの黄金時代と名づける理由はよくわかります。
ところが、70‐80年代に入り、アメリカ経済のパフォーマンスは一転悪化します。経済成長率は低下し、マイナス成長も経験することになります。重要なのは生産が停滞するもとでインフレ率が加速したことです。生産の停滞(stagnation)とインフレ(inflation)率加速の共存はスタグフレーション(stagflation)と呼ばれます。経済成長率の低下に対応して、当然失業率は上昇いたしました。この結果、インフレ率と失業率の和である悲惨度指数(miserable index)は、1980年には20%を上回る状況となりました。なお悲惨度指数については、「
現代アメリカ経済早分かり」を参照してください。アメリカ経済がこの時期低調であった理由としては、さまざまな要因が指摘されています。これについては後の章で議論しますが、そのうち2度にわたる石油危機という外的な変化を見過ごすことは出来ないでしょう。
80年代の経済混乱期を経て、アメリカ経済は再び回復の傾向を見せます。90年代にはIT革命の好循環で、経済成長率は3-4%を記録する一方で失業率は4%まで低下しました。何よりも驚くべきことはインフレ率が同時に低下したことです。この結果、高成長、低失業率と低インフレ率が共存するというこれまでに見られなかった高パフォーマンスを実現できました。アメリカ経済は大きな構造変化を成し遂げ、立ち直ったといえるでしょう。
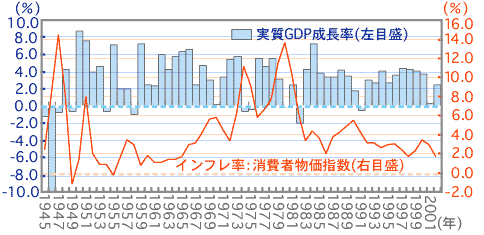 図1-1 経済成長率とインフレ率
図1-1 経済成長率とインフレ率
出所:Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics
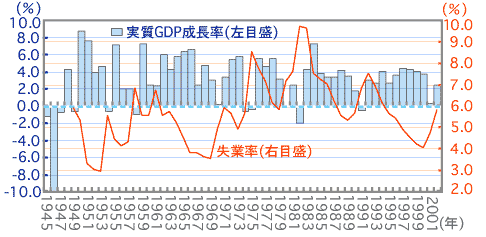 図1-2 経済成長率と失業率
図1-2 経済成長率と失業率
出所:Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics
上の2つの図からわかるように、一般的に景気がよい(経済成長率が高い)ときはインフレ率が上昇する傾向があり、また失業を引き下げる傾向がみてとれます。3番目の図は、経済成長率という共通項を介して、失業率とインフレ率の相関関係をみたもので、経済学ではフィリップス曲線とよばれます。戦後のアメリカ経済において、失業率とインフレ率の関係は一見緩やかな正の相関関係があるような気がします。これは実は誤りで、よく見ると短期的には負の相関関係にあるのです。ただ負の相関関係が時代とともにシフトしているため、長期的には緩やかな正の相関関係ないし無相関に見えるのです。
一般に、景気が後退しますと失業率が上昇します。同時に生産活動も沈滞しますからインフレ圧力は弱まり、物価には下げ圧力が強まります。したがって、失業率とインフレ率の関係は短期的には右下がりになります。この右下がりの短期的関係が石油危機の時には右上にシフトしました。図において丸で囲んだ部分がその時期に相当します。1974年から82年においては、失業率とインフレ率がともに8%を超える状況が続きます。大きな経済構造の変化があったと考えられます。石油危機が終息しますと、再びフィリップス曲線は左下にシフトし、もとの安定的な関係に戻ります。このように、アメリカ経済の動態には大きな構造的変化がともなっているのです。
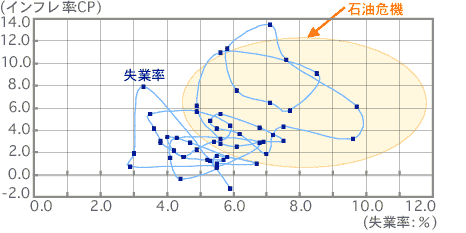 図1-3 フィリップス曲線
図1-3 フィリップス曲線